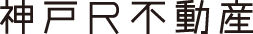高円寺アパートメント物語 vol.3 暮らしを彩る行事たち
住まい手が豊かな日常を育んでいる高円寺アパートメント。2025年5月末には隣の敷地に高円寺アパートメント2.0が誕生します。これを新たな節目として、この場所のこれまでの歩みとこれからをつづる連載コラムをリレー形式でお届け。vol.3では高円寺アパートメントの女将にバトンタッチして、高円寺アパートメントの日常やイベント、そこで育まれる関係性についてお伝えします(vol.1、vol.2はこちらから)。

2017年、vol.1のコラムを執筆した馬場正尊さんから「これからの賃貸住宅は管理から運営の時代だ」という言葉とともに「高円寺アパートメントの運営をしないか」というお話をいただいた。
建物ができて完成ではなく、人が住み始めてからが本当のスタート。どのような暮らしや関係性が育まれる集合住宅になるのか。そのプロセスに携わりたいと思い「やります!」と即答したのを覚えている。
こうして「女将(おかみ)」として、住みながら運営をすることになった。
なぜ「女将」なの?とよく聞かれるのだが、コミュニティマネージャーと呼ばれるような役割に近いと思う。ただマネジメントするというよりは、住人がやりたいことをサポートしたり、私もここに暮らす当事者として柔軟な関わり方ができたらと思い、あえて直接的な意味が分かりづらい「女将」を名乗っている。
高円寺アパートメントでは、1年を通していくつかの行事がある。マルシェやビアフェスといった地域に開いたイベントや、お花見や餅つきなどの季節行事、住人同士で楽しむ食事会など、内容も規模もさまざま。1年目は女将として私が企画していたが、現在は住人が発案して行われているものがほとんどだ。そのとき私はサポート役として参加することが多い。
ほかにも日常のなかには、住人同士や地域の人たちとの関わりや小さなエピソードがたくさんある。今回は日々の現場の目線から、この場所で育まれるライフスタイルや関係性について改めて考えてみたいと思う。

2つの飲食店と並ぶのが、4つの店舗兼住宅。ライフスタイルショップ、ジュエリーデザインアトリエ、時計修理室、そして設計事務所兼雑貨店というラインナップで、それぞれ店主が住みながらお店を開いている。
業種はいろいろだけど、どの店舗も住人の暮らしとお店との距離が近い。芝生広場で子どもを遊ばせながら店主と何気ない会話をしたり、飲食店では、住人が部屋から自分のお皿やカップを持って降りてきて、お店のカレーやコーヒーをテイクアウトして家で食べる、なんていう日常シーンもあるのだとか。
「女将」としての最初のチャレンジは、「同じ釜の飯を食べようの会」という住人同士の挨拶の場をつくったこと。入居スタートから少し経った、2017年の5月半ばの頃だった。
「同じ釜の飯を食べたら仲良くなれるんじゃないか」というシンプルな発想から、高円寺のお米屋さんでお米を買い、炊き立てのご飯を用意した。住人のみなさんには、お箸とお茶碗、一品料理を持ち寄って参加してもらうというカジュアルな食事会だ。
食事をしながら会話が生まれ、和気あいあいとおしゃべりする人もいれば、あとから聞いた話によると「大勢の住人が集まる中でのご飯会に気後れした」という人や「その後も何度か顔を合わせる機会を通してゆっくりと仲良くなった」という人もいて、関係の育み方は人それぞれ。全員が積極的にコミュニケーションを取る人ばかりではなく、それぞれのちょうど良い温度感やスピード感を大切にしながら関わり合えることも大切なのだと実感した。

「同じ釜の飯を食べようの会」をきっかけに新たなイベントが誕生した。1階で新たにお店を始める住人と意気投合し、高円寺アパートメントのことを知ってもらう機会をつくろうと「高円寺アパートメント おひろめマルシェ」を企画した。
いい意味でカオスで“ディープなサブカルチャー”という印象が強いこのまちで、高円寺アパートメントは芝生が豊かで穏やかな雰囲気なこともあり、近所の方々から高円寺らしくない場所という印象を持たれていた。そこで「この場所も高円寺らしさの一つだと思ってもらえるようにしよう」と、まちに開いて開催した。
出店者は知り合いに声をかけ、装飾などは住人たちにも手伝ってもらいながら、準備をしていった。「人が全然来なかったらどうしよう…」とドキドキしながら当日を迎えると、予想に反して多くの人が来場し、まちの人たちの期待を感じることができる1日となった。

「おひろめマルシェ」以降も定期的にマルシェを開催し、現在は春にマルシェ、秋にビアフェスを開催している。継続していく中で大切にしているのは「自分たちの暮らしを自分たちで楽しくする」こと。自分の趣味を披露したり、子どもたちも主役になれたり、まちの人たちと関わり合える機会になったり。毎回開催前に作戦会議を開いて、どんな内容にしたいか、どんな出店やコンテンツがあると良いかを話し合っている。
マルシェが恒例行事となってきた頃、コロナ禍となり2年ほど開催できない時期が続いた。コロナが落ち着いてから再開できたものの、コロナ禍に新たに引っ越してきた住人たちはマルシェを体感したことがないため、つくり出したい風景を共有するのが難しい状況だった。また、高円寺アパートメント自体はまちに浸透し始めていたこともあり、「地域に知ってもらいたい」という当初の目的から変えていく必要があった。
そこで「なんのためにマルシェをするのか?」について改めて考える作戦会議を開いた。新しい住人にもまちの人にも高円寺アパートメントの暮らしを知ってもらうことに加えて、関わりたい人が関わりやすい仕組みを考えていくことになった。
具体的には、高円寺アパートメントのこれまでが分かる年表や住人おすすめのお店のマップを作成したり、住人のインタビューやお部屋のイラスト、模型を展示。マルシェの数週間前から住人たちで集まってマップをつくり、当日参加できない人も関われる機会をつくった。

ほかにも当日には住人のフリーマーケットを開催し、その中で販売するものにストーリーを書いて出品してもらったり、おすすめの本の展示をしたり、DJブースで好きなプレイリストを流したり、さまざまな参加の仕方ができるように住人たちでアイデアを出し合って準備を行っている。

マルシェ以外にさまざまな季節行事も開催してきた。2年目である2018年の新年会で住人たちと高円寺アパートメントでやってみたいことを出し合い、住人同士で協力し合いながらアイデアを実現していった。
これまで開催した行事は、お花見や流しそうめん、縁日、納涼会、忘年会、お餅つきなど。その後も毎年、年のはじめに作戦会議を行って「今年どんなことをしたいか」を話し合ったり、突発的に生まれる「こんなことをやってみたい!」という行事が恒例化することもある。

お花見は出かけるのではなく、「桜の枝を買ってきて芝生でやろう!」というアイデアから気軽に参加できるものになったり、お餅つきは近所のお米屋さんに協力してもらったり、コロナ禍で飲食を伴う集まりは難しいからと子ども向けの縁日を考えてみたり。まずは動きながら、できる方法を住人たちで考えて進めていった。
さまざまな交流の機会をつくる中で大切にしたのは、強制しないこと。全員参加だと気が重くなってしまうし、参加できなかったときに疎外感が生まれてしまうので、「来られたら来てね」という温度感でお誘いしている。
季節行事を開催していて感じるのは、複数の家庭が集まることで暮らしを楽しむ可能性が広がるということだ。流しそうめんや縁日、お餅つきなどはみんなで集まって、近所の方の力も借りながら準備するからこそ実現できたもの。
誰かと関わり合い、協力し合うことで、1人や1つの家族だけではできないことが実現でき、日常や暮らしがちょっとずつ楽しくなっていく。そんな暮らしが高円寺アパートメントでは生まれている。

マルシェや季節行事などを通して仲が深まることもあれば、日常的な関わりを通じてゆるやかに関係性が育まれることもある。お互いの家で食事をしたり、子ども同士が芝生で一緒に遊んだり。個人的には、集合住宅という独立した住戸に住みながらも、同じ屋根の下で“ともに”暮らしている感覚もある。
特に実感したのはコロナ禍のときだ。不要不急の外出を避け、家からあまり出なくなったことで、ひとり暮らしの人は誰とも話さなかった日が続いたという人もいるだろう。
一方で高円寺アパートメントでは、散歩や買い物に行くときに芝生を通ると他の住人とすれ違ったり、距離を保ちつつ挨拶やちょっとした会話ができたり、新鮮な野菜などを共同購入して分け合ったり。私自身、1人で暮らしていても独りではない感覚が、とても心の支えになっていた。
子どもがいる世帯も、芝生広場に行けば誰かがいて一緒に子どもと遊んでくれたり、親同士で情報交換ができる環境をうれしく感じてくれているようだ。2017年のスタート当時は子どもがいる家庭が1世帯のみだったが、現在は10世帯ほどに増えている。

顔の見える関係性が育まれているので、サイズアウトした洋服や使わなくなったベビー用品をお下がりしあったり、ときには親御さんの代わりに他の住人が保育園の送り迎えをしたり。「お互い様」と支え合える関係性が育まれているのを感じる。
有事にも支え合える関係性として、災害時の共助についても住人たちで話し合った。2021年、地震が多発した時期に住人の1人から相談をもらい、住人たちと防災ワークショップを企画。事前の備えや地震など災害時の対応、どう助け合えるかなどの仕組みについて考えた。
その後、住人の有志メンバーで防災マニュアルを作成し、現在は住人主催の防災訓練も行っている。防災訓練では、マニュアルの内容を忘れないために読み返したり、避難場所である近所の小学校に行ってみたり、非常食を調理してみたり。個人でやるには少し面倒で重い腰が上がらないことも、みんなでやることで楽しみながら取り組める。

多種多様なイベントや季節行事、防災訓練などを行っているが、人によって関わり方はさまざまだ。
企画などをコアになって関わる人、集まりには参加する人、参加したり、参加しなかったり、まったく参加しない人。ライフステージの変化によっても関わり方がゆるやかに変化している。
これまでの自治会のような窮屈さではない、それぞれの心地のいい距離感を大切にした今の時代にあった新しい「くらしの自治」が高円寺アパートメントでは生まれつつあると思う。
昔の長屋のようにどこか懐かしくもあり、ちょっと新しい暮らし。
家族という最小単位のコミュニティより広いけど近すぎず、ご近所さんほど遠くはない。「家族とご近所さんの間の関係性」が育ってきている。
そんな関係性の中で共助が生まれて、安心感や愛着も育まれる暮らしの場となり、住まい手自らが自分たちの暮らしを自分たちで楽しくしながら、住まいの価値を高めている。

高円寺アパートメント2.0が誕生し、新しい住人が加わることでどんな関係性が育っていくのか。正直、ドキドキしている。
ふたり暮らしやファミリーが多い1.0に比べて、2.0はひとり暮らし用の部屋が多い。ライフスタイルがますます多様になり、1.0と2.0が交わって新たな生態系に変化していくかもしれない。まだ見ぬ高円寺アパートメントの未来の暮らしに思いを馳せながら、ここに集う人たちと、この場所だからこそ生まれる等身大の日常を一緒に育んでいきたいと思う。
女将は、高円寺アパートメント1.0の1階で、ライフスタイルショップ「まめくらし研究所」を営んでいます。高円寺アパートメントの雰囲気を体感してみたい方、2.0についても気になることがあれば、お店に気軽に立ち寄ってみてください。
このコラムは次回で最終回。「高円寺アパートメントのこれから」をテーマに、設計者目線から建築デザインを紹介しつつ、1.0から2.0へとつながる構想や企みについても掘り下げていきます。
高円寺アパートメント
高円寺アパートメントウェブサイト
高円寺アパートメントInstagram
 関連コラム
関連コラム
 おすすめコラム
おすすめコラム







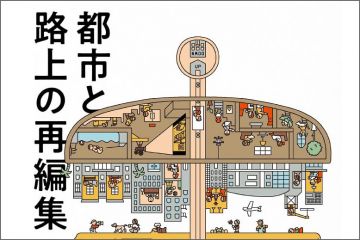






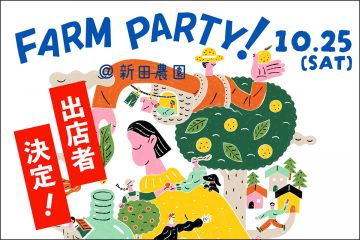




























![[団地を楽しむ教科書] 暮らしと。](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/rincglobal/common/thmb_kurashito_book.png)