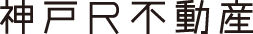どこに住んだらいい? 京都適所探しの指南書
金沢、福岡、稲村ヶ崎、神戸、大阪、鹿児島などでR不動産が生まれ、さまざまな土地で僕らは住まい方を発見してきました。そして今秋、京都R不動産がスタートします! それに向けて、集中連載をお届けします。まずは「京都、どこに住めばいいの?」から。
 三方を山に囲まれ、視界を遮る高い建物がない京都の街の景色。
三方を山に囲まれ、視界を遮る高い建物がない京都の街の景色。この言葉は知り合いの何人かから言われたものだ。平安京以来の長い歴史を持つ“古都”というイメージが強いかもしれないが、実は意外と街は広く京都の中でもエリアごとにかなり性格が違う。だからこそ、ひとくちに京都と言っても、どんなエリアがあって、どこに住めばいいのか、みなさん迷うようである。この問いかけに応えるために、京都の街の成り立ちを紐解かないといけない。そう思って、手始めにこのコラムを書くことにした。
僕は生まれてから大学まで京都で、卒業後東京で10年間働き、いわゆる「Uターン移住」という形で、地元に帰ってきた。卒業するまでは実家暮らしだったので「自分で住む場所を探す」ということはしてこなかったが、今回戻ってきて自分の意志で「京都のどこに住むか」を決めた。
僕が選んだのは西院というエリア。京都の中でもローカル色が強く、例えば飲み屋には地元の人がワイワイ集っていて、1軒目も2軒目も3軒目もこの街の中でまかなえてしまうような、そんな活気がある街。そういう下町的な雰囲気にして、京都駅や大阪へのアクセス、高速道路へのアクセスも良いという面白い場所だ。
 西院駅前と裏通り
西院駅前と裏通りどこかの会社に入るわけではないし、決まった場所に毎日通わなければいけないということもなかった。また物件も賃貸で探していたので、比較的自由度高く場所を選択できたかなと思う。ただ、東京生活が長かったこともあって、京都以外の場所や人とのつながりについてもつくりやすかったり、出張で東京へ行ったり中部や西日本にもパッと行きやすい、“フットワークの良い場所”であるという点は意識した。あとは生まれた場所も東京時代も静かな住宅街だったので、あえて違う雰囲気の場所に住んでみようと思った。
実際に住んでみると、思った通り、前に住んでいたところとは違って、朝も夜も街と人が常に動いていて今の自分にぴったりだった。静かに暮らすより賑わいのある場所の雰囲気を生活に感じていたかったし、京都府外に出るのもかなりスムーズだ。
「駅から徒歩●分」のようなアクセスの情報だけではなく、エリアごとの“色”がわかると、僕のようなUターン移住者とか、あるいは京都出身者ではないIターン組や、中長期の滞在をする人たちにも役立つのではなかろうか。
というわけで、何回かにわたって、連載の形で京都のエリアの説明をしていこうと思う。 次回からはエリアごとで物件も紹介する予定だが、最初となる今回は、京都の街の基本的な情報側面から伝えていきたい。
まず、京都の街のサイズ感をイメージできる人はどのくらいいるだろうか?
実際に調べてみると、京都の中心部は、東京のJR山手線の内側に近いサイズ感になる。その範囲の中に、清水寺がある東山の歴史的美観地区があったり、織物の町「西陣」の小さな工場が集まるエリアやサブカル聖地の左京区エリア、緑豊かで閑静な住宅街が広がる北山エリアなど京都の主要なエリアがすっぽり入っている。
 現在の行政区(白線)やランドマーク(黄色)に、山手線の線路(赤線)を重ね合わせてみる。青線は河川。黒線は京都線(京都-大阪間)/JR琵琶湖線(京都-滋賀方面)。(画像 ©2016 Google、地図データ ©2016 Google、ZENRIN)
現在の行政区(白線)やランドマーク(黄色)に、山手線の線路(赤線)を重ね合わせてみる。青線は河川。黒線は京都線(京都-大阪間)/JR琵琶湖線(京都-滋賀方面)。(画像 ©2016 Google、地図データ ©2016 Google、ZENRIN)このサイズ感には理由があって、それは約1200年前、風水学的に吉ということからこの地に平安京都が置かれた歴史的背景とつながっている。“繁栄する場所”に必要な「四神相応」の思想と当時の京都の地形が合致していて、北の丹波高地が玄武、大文字がある東山(及び鴨川)が青龍、西の嵐山が白虎、南の巨椋池が朱雀、とそれぞれの方角と地勢を司る四つの神がいるとされた。
噛み砕いて言うと
・三方(東西・北)を山に囲まれている
・街の中心に川が流れている
・南側は広大な平野が続いている
ということになる。
特に最初の地理的な理由から、京都は人口がどんどん増えていく過程で一定エリアまで街が拡大すると、盆地を囲む山のせいでそれ以上街が広がることができなかった。ある意味、エリアはロック(固定)された状態で、その中で人の営みが生まれては、入れ替わり……、そのようにして千年を超える歴史が積み重ねられたのだ。
“誰でもが顔見知り”というほどコミュニティーが小さくもないし、移動がおっくうになるほど大き過ぎもしない。そんな中で歴史の厚みの分だけ多様なコンテンツが新陳代謝しながら発展し続けて今に至る、それが京都という街なのである。
 京都の街中を流れる鴨川(左)と出町柳以北を流れる緑豊かな賀茂川(右)。同じ"かもがわ"でも表記が異なる。
京都の街中を流れる鴨川(左)と出町柳以北を流れる緑豊かな賀茂川(右)。同じ"かもがわ"でも表記が異なる。「洛中洛外図」という屏風を見たことがある人もいるかもしれない。戦国時代から江戸時代にかけてたびたび制作され、その一部は国宝や重要文化財になっている金の屏風である。時代とともにその対象範囲は変化していっているが、豊臣秀吉の時代にはその内外を「御土居」と呼ばれる高さ3メートルほどの土手で物理的に区切ったこともあったという。今でも地名として残っている、丹波口・荒神口・鞍馬口、などは洛外から洛中への入口の名残で、夕方になると門が閉められ出入りができなくなっていたようだ。
 「洛中洛外図」(国宝) 米沢市上杉博物館蔵
「洛中洛外図」(国宝) 米沢市上杉博物館蔵地元のおばあちゃんなどと話をすると、「私は洛中の人間やで。あんたはどこや?」と言われることがあるが、洛中すなわち京都の中心部に住んでいる人はそのことがプライドだったりする。僕は洛外の出身なので、「洛中の方にはかないません」としっかりと“立てる”ことを忘れないようにしている(笑)
住むという尺度で京都を見つめ直したときには、やはり洛中の方が付き合いとかコミュニティーの粘性は高くなる気がする。街のコアなエリアになればなるほど、ちゃんとしなきゃ、みたいな。がっつり京都を感じるなら洛中へ、少しラフに京都に住むなら洛外、そういうイメージ。ちなみに僕の感覚で、今京都で面白い場所はちょうど洛中と洛外の境にあるエリア。かつての街外れでたぶん治安もあまり良くなかった場所だけれど、そのエリアの持つ煩雑で京都っぽくないちょっと歪んだ感じが新しい表現を生む土壌になっていて、洛中と洛外という区分けが今の時代にも影響していることを感じる。もともと平安京が置かれたとされるエリアが以下の地図。都があった当時の洛中のエリアがどこまでかがわかる。
 現在の京都の主要ランドマークと行政区分けを入れた地図に、かつての洛中のエリアをはめ込んだ。(画像 ©2016 Google、地図データ ©2016 Google、ZENRIN)
現在の京都の主要ランドマークと行政区分けを入れた地図に、かつての洛中のエリアをはめ込んだ。(画像 ©2016 Google、地図データ ©2016 Google、ZENRIN)多様で混在、京都に住んでいると実感することである。ひとつの要因はさっき書いた、地理的に「街が大きくなり過ぎなかったこと」、そして「大規模な戦火を免れかつての街の形が残っていること」である。
いわゆる大規模な都市計画的なものが行われたのは、平安遷都のときと豊臣秀吉が国を治めた時代の2回で、後者でも今からさかのぼること400年強も前の話。更地からの再開発という場所もほとんどない。それが今の街にどう関係しているかというと、京都は「住宅街」「繁華街」「工場街」といったエリアごとの役割の線引きがとても曖昧。この曖昧さが、京都の醍醐味と言ってもいい。神社仏閣の周りに仏具を取り扱う店が集中している、とか、西陣に織物関係の商いが多い、とかそういうことはあるけれども、全体的にはゴチャッとしていて、住宅もお店もオフィスも混在している。
言い換えれば、今でも自分で小さな商いをしている人たちが本当に多い。そして「京都は京都の中で経済が回っている」と言われる。街のサイズ感もちょうど良くて移動コストも少なく、地域で小さな経済を回している、そういう街。
 織物工場や製紙工場が多くある西陣エリア。戦火を免れたからこそ、昔と同じ暮らしの風景が残っている。
織物工場や製紙工場が多くある西陣エリア。戦火を免れたからこそ、昔と同じ暮らしの風景が残っている。また近年「職住一体」の暮らしにスポットがあたっているけれど、元々京都は職住一体で、建物の前や1階で商いをして、奥や2階に住むスタイルがあり、そうした建物の使われ方が今でも珍しくない。そして働くところと住むところが近いと、仕事をしている人もいれば学校帰りの子どもたちもいる、ずっと昔から住んでいるおばあちゃんが道端で談笑している姿にも出会う、街がそんな景色になる。みんな混在して一緒に生活している感じ。
 左は扇子屋。右は昆布屋。京都の街を歩けば見かける「職住一体」のスタイル。
左は扇子屋。右は昆布屋。京都の街を歩けば見かける「職住一体」のスタイル。さらに、いろんなバックグラウンドを持った人たちの外からの流入が非常に多い街でもある。世界各国からの観光客、外国人の留学生、大学や企業の研究員・先生、アーティスト……。彼らは日本を知ろうとして来ている人たちであることが多いので、地元の人とも積極的に交流している。
この玉石混交さが京都の街で暮らす醍醐味かもしれない。
夏は高温多湿の盆地気候、冬は「底冷え」といわれる寒い日が続く街、京都。地理気候風土的な要素だけを見ると、ちょっと腰が引けてしまいそうであるが、夏は川のせせらぎの上に床をしつらえた川床で涼を取ったり、冬は何気なく入った料理屋さんに火鉢が置いてあったりと、それぞれの季節もちゃんと楽しめる風情と知恵で四季の変化を感じることができる良さがある。
ちょっと脱線してしまったが、「京都、どこに住んだらいいのか」、まずは、街のサイズ感とその成り立ち、玉石混交さについて伝えたかった次第だ。
「京都R物件特集」は、2~3週間ごとに継続的にコラムで展開していく予定。
第2回からは、具体的に京都をいくつかのエリアに分けて、より詳しくそのエリアの特徴と物件を紹介していくので、どうぞお楽しみに!
◆物件オーナーの方へ
東京R不動産では掲載物件を募集しています
物件の掲載自体に費用はかかりません。成約時にのみ手数料をいただいております。
「物件活用相談・コンサルティング」も受付中です
貸し出し前のリフォーム・リノベーション、賃貸物件の企画や設計などはこちら。
 連載記事一覧
連載記事一覧
 おすすめコラム
おすすめコラム











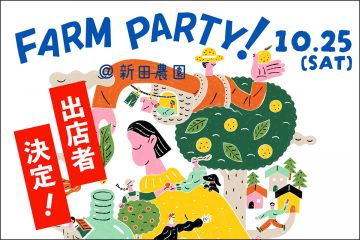































![[団地を楽しむ教科書] 暮らしと。](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/rincglobal/common/thmb_kurashito_book.png)