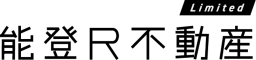小谷さんと小上がりのある書店「葉々社」
語り手:小谷輝之さん

品川駅の京浜急行のホームに立つと、いつもどこか不安な気持ちになる。飛行機の搭乗時間を気にして時間に追われているか、初めて行く場所に向かっていることが多いからだろう。平和島で乗り換えをして、降りたのは梅屋敷という駅。20年近く東京に住んでいるけれど、初めて降りる駅だ。
向かう先は、2022年4月に開業した書店「葉々社」。東京R不動産で募集した物件だ。選書に店主の個性が光る「独立系書店」の一つである。聞くところによると店主の小谷さんは梅屋敷には縁もゆかりも無かったという。小谷さんがこの場所に根を下ろして小さな書店を営む理由が知りたくて足を運んだ。
梅屋敷の駅前から伸びるのんびりとした商店街を歩く。平日の午前10時前だから開いている店は少ないけれど、駅に向かう人や散歩をしているお年寄りの姿が見られる、ちょっと下町っぽい風情を感じるまちだ。商店街を5分ほど歩いて角を曲がると、「本」と書かれている、昔ながらのまちの本屋にあったような看板が見える。潔い看板のデザインに、入る前から好感を持ってしまう。
ガラス引き戸の入口には、書店らしからぬ緑色の暖簾がかかり、チラチラと店内が見える。外から丸見えではないけれど中の様子がわかるし、「どうぞお入りください」という店主の心意気が伝わってくる。引き戸をあけると、店主の小谷さんが本に囲まれたちいさな小上がりから顔を出して、中に招き入れてくれた。

ちょっと柔らかい大阪弁で話す小谷さんは、大阪の東大阪市で生まれ育った。東大阪市はものづくりのまちと言われていて、人情味溢れる大阪の下町だ。書店を開くぐらいだから、生まれながらの本の虫タイプかと思いきや、自宅にたくさん本があったわけでもなく、外遊びが大好きな活発な少年だったようだ。約40年前、ゲームもないしインターネットもない時代。ボール投げや鬼ごっこをして、友達同士で日が暮れるまで外で遊んでいた。働き者だった両親は家を空けることが多く、外で遊ぶ以外の時間は、学校の図書館で借りた鉄道や動物、日本の歴史の本、世界の偉人シリーズなどの本を読んで過ごした。
「気がついたら本はわりとずっと近くにあったんですよ。おとなしい文学少年みたいなタイプじゃないんですけどね」
地元の男子高に進み、同級生に『ノルウェイの森』を勧められて読んだときには、その鮮烈な描写に衝撃を受けた。本はいつだって自分を少し物知りに、そしてちょっと大人にしてくれる存在だ。

京都の大学に進学して、通学の電車のなかでは週刊誌のAERAを読んだ。1990年代に書店の売上を支えていた週刊誌は、ありとあらゆるジャンルの情報が掲載されていて、新聞を読まなくても時事ネタまで網羅できる貴重な情報源だ。いつしかAERAに記事を書くようなジャーナリストになりたい、と思うようになり、出版社志望で就職活動をして、とあるテレビ関連の週刊誌の編集部で働くことになった。
1990年代はまだまだテレビ業界が元気で、発売日にはテレビ関連の週刊誌が書店やコンビニに何種類も並んでいた時代だ。テレビ局に出入りすることも多く、泥臭い現場でとにかく忙しい日々。家に帰る暇もないような20代を過ごす。
だが、30代も半ばに差し掛かった頃、週刊誌編集の渦中で過ごすうちに考え方が変わり、雑誌の大量生産大量消費に抗いたい気持ちが出てきた。毎週90万部発行される週刊誌が、刷られては捨てられていく世界に違和感を抱いたのだ。読み捨てられるものではなく、人の心を動かす、手元に長く置いてもらえるものを作りたいと考えるようになる。
「好きなのは、遠藤周作、開高健、司馬遼太郎の歴史文学やノンフィクション。海外文学も読みます。自分に知識を与え世界を広げてくれた本は、いつまでも色褪せないし傍に置いておきたいですよね」

そう思い立って、会社を退職後、書籍をつくっている出版社を数十社受けたが、なかなか転職先が決まらない。そんな折、あるカメラ雑誌の編集部の契約社員募集に応募したら採用してもらえた。カメラも好きだったし、テレビ週刊誌よりも楽しそうに見えた。
仕事は真面目に一生懸命やるタイプだから、やがて正社員になりそれなりに評価もされた。40代のときには希望を出して2年間のシンガポール赴任も経験し、一度は海外で働いてみたいという夢も叶う。最終的にカメラ雑誌の副編集長にまでなったが「書籍をつくりたい」という思いはずっと頭の片隅でくすぶっていた。特に、シンガポールでのネットコンテンツの編集経験は、小谷さんの紙の本づくりへの渇望をさらに強いものにした。モニターのなかで1ページにきれいにまとまったコンテンツはダイナミズムに欠けるし、ページをめくる楽しさもない。工夫の凝らしようもなく、セオリー通りにものをつくるのはとても退屈だった。やっぱり紙の本を作りたい、さてどうしよう...?

紙の本を作れる部署への異動も考えたが、結局編集長になれなければ裁量権もない。転職活動をして別の出版社に入っても、やりたい本づくりができるかどうかはわからない。長いサラリーマン経験から、裁量を持ち自由に仕事を進めることの難しさはよくわかっていた。だったら、自分だけで作りたい本を出版する「ひとり出版社」をやるのもありなのでは?と思い立つ。
ひとり出版社の知り合いもいるし、ノウハウも人脈もある。自分も出版社をやろう!と決意してリサーチを始めてみると、ひとり出版社の方たちが良い本をたくさん作ってることにはじめて気づいた。彼らは自分の信念に基づいて本を作るからブレがないし、この本を作らなければ!という切羽詰まった事情や情熱がある人も多い。
「自分がやるべきことは“ひとり出版社”が手掛ける良書を売る場所、つまり本屋をつくることだと考え直したんです」
もともとジャーナリスト志望で、知的好奇心を満たすものとして書籍や雑誌を手にとってきた小谷さんだ。社会的意義の視点から、そんなふうに考えるのは当然の流れだったのかもしれない。

20年前、いわゆるまちの本屋は約2万店あったそうだ。小売業は店主の目利きが勝負だが、実は一般的なまちの本屋にはそれがあまり必要ではない。取次店から次々入荷する人気の週刊誌や話題の新刊を書棚に並べておけば、発売日には勝手に売れていく。本屋を始めるのは難しいことではなく、粗利がたった22%でも返品が可能なため商売が成立し、一昔前まではちいさなまちにも必ず本屋があった。今では、本屋の数は約1万店に落ち込んでいる。そんな時代に、じわじわと増えているのが「独立系書店」と言われる現代版のまちの本屋だ。ネット書店や大型書店が主流となっている今、独立系書店では店主の選書の目利きと、書籍販売以外のビジネスが勝負になる。
独立系書店の開業を志した小谷さんが描いた物件の条件は、こんな感じだ。
・自宅から自転車で通える場所
・小上がりがある物件。子どもたちが気軽に立ち寄れるように
・一人で目の届くコンパクトなサイズで、安い家賃
長年の出版社勤めの経験と周りの人たちからのヒアリングで書店開業のノウハウはある程度わかっていたが、問題は物件探しだった。もともと小上がりがある店舗物件というのは実はそう多くは存在しない。スケルトンの状態で借りて小上がりを造作するのが一般的な気もするが、小谷さんには当時そういう発想がなく、小上がりありきの物件を自宅の近隣エリアで探していた。もちろんなかなか見つかるはずもなく途方に暮れていたら、知人の写真家の夫妻が「東京R不動産に小上がりつきの店舗物件が載っていた」と教えてくれたのだ。
「東京R不動産のことも知らなかったし、梅屋敷は降りたこともない駅。でも、自宅からもそう遠くなく条件が良かったので、すぐに問い合わせをして内見に行きました」

内見後、同世代のオーナーとの面談で「書店を開きたい」と伝えたら、この町には本屋がないから嬉しいと言ってもらえた。一方で「商売をするのに本当にこの場所でいいのかは、よく考えて欲しい」とも。
面談後、オーナーの「よく考えて欲しい」という言葉を反芻しながらまちを歩き、物件近くのカフェに立ち寄った。店内には女性がぽつぽつと4人ほど座っていて、それぞれが本を読んでいる。どんなまちにだって本が好きな人は一定数いるはずだし、あたらしい事はどこで始めたとしてもどう転ぶかはわからない。まちに本屋が必要だと考えて背中を押してくれる人がいるなら、ここで始めてみよう、そう思えた。
R不動産に掲載されていた小上がり物件を契約して、いよいよ「葉々社」がオープンしたのは2022年のことだ。
葉々社はいくつかの商いの組み合わせでできている。
・新刊、古本の販売
・ギャラリーのように壁を貸す
・一箱のスペースをシェアする貸し本棚
・ちょっと気の利いた雑貨の販売
・飲み物などの軽飲食販売
そして、小谷さんのひとり出版社としての仕事と、自ら筆をとる原稿執筆の仕事が組み合わさって、葉々社は成り立っている。
「場所の存在はやっぱり大きいですね。やれることが広がるし、この場所が本と人をつなげて、人と人をつなげることができます。」
葉々社という場所をベースに、このまちで何ができるかを考える日々はとてもクリエイティブだ。

ここは本屋でありながら、本を売っている場所と定義するのも少し違うように思えたから、「小谷さんはこの場所で何を売っていると思いますか?」と聞いてみた。すると「いろいろやっていても、やっぱり僕は本を売っているんです」という答えが返ってきた。
「本はネットの記事とは違って、一定のクオリティを担保する過程があるし、横への広がりも縦への深さもある。みんなにいい本を手にとって欲しい、そして本を通して“考えるきっかけ”を手に入れて欲しい。それが、僕の最大の目的なんです」
葉々社は10坪ほどの決して広くはない書店だが、小上がりを境に少しだけ雰囲気が違う。手前の書棚のエリアは、いい意味でニュートラルで真面目。行儀よく並んだ背表紙には、哲学書や小谷さんが好きな歴史文学にまつわるタイトルもあり、文芸を通して社会の抑圧や闇に光を当てる韓国文学のコーナーもある。小谷さん自身も編集者として出版に関わる韓国文学は、まさに考えるきっかけを与える本だろう。

一方、編集者で書き手で書店経営者の小谷さんの仕事場でもある小上がりは、ちょっと雑多な空気感を醸している。壁一面に貼られたメモ書きに、棚主が選書する貸し本棚やギャラリー風の壁もあり、いろいろな意味でカラフルな空間だ。懐かしさを感じるちゃぶ台に座布団、手作りのZINEや雑貨も並び、葉々社の懐の深さを感じられる。
開業して2年が経ち、毎月、毎週のように訪れる常連さんも多い。近所に葉々社ができたことがきっかけになり、本をたくさん買って読むようになったお年寄りもいるし、応援の意味でわざわざ葉々社で本を買ってくれる人もいるそうだ。小谷さんが選ぶ本たちが、まちの人たちの人生をそっと豊かにする。葉々社はそんな場所になっているように思う。

さて、この小上がり物件のオーナーは、R不動産のコラムでも紹介した茨田さんである。
茨田さんは、過去にパン屋さん限定でテナントの入居者を待ち続けたことがあるオーナーだ。自分の物件を借りてくれる事業者や住まい手たちが、まちの空気をつくっていく。そのことをよくわかっているから、単に空き物件が埋まればいい、という考え方で募集はしない。まちにとって良い影響のあるお店や人に物件を借りて欲しいという思いを込めて、R不動産に物件を掲載してくれている。
そんな、オーナーの思いが込められた物件が借り手を引き寄せる、ということがあるのだと思う。
小谷さんが「小上がり」の物件での新たな人生と日々の風景を想像していたとき、同時に茨田さんはそんな風景とまちの姿を想像していたに違いない。小谷さんにとって梅屋敷という街は“縁もゆかりもなかった”けれど、葉々社がここに開いたことに、きっと、理由はあったのだ。そしてもし、R不動産という場がその引き寄せの力を手助けできているとしたら、こんなに嬉しいことはないだろう。
最近はすっかりスマホに時間を取られてしまい、本を読む機会が減ってしまった筆者だが、ひとたび書店に入れば本を買わずには店から出られないような本好きである。もちろん葉々社でも、書籍の匂いにクラクラし、帯に踊るコピーや美しい装丁に心を奪われ、そんなつもりではなかったのについつい数冊自宅に連れて帰ってきてしまった。葉々社は、私にもあたらしい出会いと考えるきっかけをもたらしてくれた。

語り手:小谷輝之さん
葉々社:https://youyoushabooks.stores.jp/
取材・構成:矢崎 海 / 写真:阿部 健二郎
-
 Vol.007安藤さんと大蔵の地語り手:安藤勝信さんあとから来るもののために100年後に思いを馳せる。安藤さんと大蔵の地の物語
Vol.007安藤さんと大蔵の地語り手:安藤勝信さんあとから来るもののために100年後に思いを馳せる。安藤さんと大蔵の地の物語 -
 Vol.006杉田さんと「アカバネの森」語り手:杉田由樹さんクリエイティブなオーナーたちが生み出す、他にない物件。杉田さんと「アカバネの森」の物語
Vol.006杉田さんと「アカバネの森」語り手:杉田由樹さんクリエイティブなオーナーたちが生み出す、他にない物件。杉田さんと「アカバネの森」の物語 -
 Vol.005小谷さんと小上がりのある書店「葉々社」語り手:小谷輝之さん思いが込められた物件が、魅力的な借り手を引き寄せる。小谷さんと梅屋敷「葉々社」の物語
Vol.005小谷さんと小上がりのある書店「葉々社」語り手:小谷輝之さん思いが込められた物件が、魅力的な借り手を引き寄せる。小谷さんと梅屋敷「葉々社」の物語 -
 Vol.004中屋さんと「わたしの熱海の家」語り手:中屋香織さん移住は理想の暮らしを手に入れる手段。熱海で自分らしい暮らしを手に入れた中屋さんの物語
Vol.004中屋さんと「わたしの熱海の家」語り手:中屋香織さん移住は理想の暮らしを手に入れる手段。熱海で自分らしい暮らしを手に入れた中屋さんの物語 -
 Vol.003街のささやかな革命家語り手:河野健昇さん・河野陽子さん豊かな空間で街を変えていく。郊外でリノベ再販事業を手掛ける建築家夫妻の物語
Vol.003街のささやかな革命家語り手:河野健昇さん・河野陽子さん豊かな空間で街を変えていく。郊外でリノベ再販事業を手掛ける建築家夫妻の物語 -
 Vol.002麻生要一郎さんと「カスティロ」語り手:麻生要一郎さん新・雑居世界のはじまり。麻生要一郎さんとマンション「カスティロ」の物語
Vol.002麻生要一郎さんと「カスティロ」語り手:麻生要一郎さん新・雑居世界のはじまり。麻生要一郎さんとマンション「カスティロ」の物語 -
 Vol.001江頭さんと「DOTEMA」語り手:江頭豊さん物件と人の物語を綴るコラム第1回。東京・池ノ上に佇む複合スペース「DOTEMA」の物語
Vol.001江頭さんと「DOTEMA」語り手:江頭豊さん物件と人の物語を綴るコラム第1回。東京・池ノ上に佇む複合スペース「DOTEMA」の物語


















![[団地を楽しむ教科書] 暮らしと。](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/rincglobal/common/thmb_kurashito_book.png)