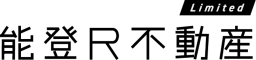街のささやかな革命家
語り手:河野健昇さん・河野陽子さん

「安い家を探して、安い壁紙を貼り直して、少し高く売るのではダメなんです。時間の無駄で、やる意味がない。僕たちが、自分で住みたいと思えるぐらいまで仕上げて、その価値をわかってくれる人に売りたいんです」
郊外でマンションの再販(自ら買い取り、リノベーションで価値を高めて販売する事業)をしているご夫妻がいると聞いた。さっそく掲載されている物件情報を見ると、居心地がよさそうな良質な空間を持つマンションだ。何気ないというか、肩に力の入ったデザインではない。場所は“入間市”。僕たちがそれほど得意としていない郊外型ベッドタウンに、良い意味で「ささやかで素敵な物件」を繰り返し再販しているということに興味を持ち、訪問させていただくことにした。
池袋駅から運よく特急に乗れれば30分。入間市駅の南口を出て、緑あふれるけやき通りを10分ほど歩いた先のマンションの一階に、壁一面のガラス窓を持つギャラリーがある。通りからも覗き込める小さいながらも開放的な空間では、季節に応じてアーティストの作品が飾られる。
ギャラリーに入り、さらに奥のドアの先に、二人とも建築家である河野さんご夫妻の仕事場が突如出現する。壁の一面は作り付けの本棚で、ぎっしりと建築関係の本が詰めこまれている。天井からは謎のオブジェがぶら下がり、模型が壁にかかっている。すっきり整理された空間ではないが、不思議な居心地の良さ、そして同時にワクワク感が漂う。まるで秘密基地のようだ。

痩身の河野健昇さん(次項以降、健昇)は、スタイルがよく背が高いロマンスグレー。やや早口ではあるが言葉を選んでロジカルに話をする。河野陽子さん(次項以降、陽子)は対象的に情熱的で機関銃のようにセンテンスを紡ぐ。健昇さんのことは「ケンさん」と呼ぶ。
健昇さんは、日本を代表する建築家の一人であった故・池原義郎氏の大番頭として、西武球場や西武遊園地など大型建築プロジェクトを次々と成功に導いた立役者だった。その彼が、パートナーの陽子さんと共に、数十年にわたる第一線の建築家としての経験を経て、どうして、この秘密基地で個人による個人を対象とした不動産再販を行うことになったのか。その疑問に迫るために二人へのインタビューを始めた。
最初は、二人のリノベ再販事業の話を中心に聞くつもりだった。しかし、その前段として聞いた二人の現在に至るまでの波乱万丈な道のりが余りにも興味深く、そしてその歴史こそが現在の事業の形につながっていることを知った。本コラムでは少し長くなるが、まず、お二人のライフヒストリーを描き、後段でリノベ再販についてまとめたい。

島根県の青年が東京で建築の中心に
島根県の小さな町の鉄工所に生まれた健昇が、早稲田大学の建築学科に進むことを決めた1970年代は、高度経済成長の喧噪の中で、丹下健三をはじめとする綺羅星のような建築家たちが脚光を浴びていた時代だ。
だが建築を学び始めた健昇には、建築界の名門である早稲田の教授陣の作風は、余りに合理的・機能的なアプローチに偏り、いわば詩情に欠けているように感じられた。その中で、ただ一人、感性を重視し、詩的な建築を創る池原義郎教授の研究室を選んだのは当然の選択だった。ちょうどこの頃、40代半ばの池原は所沢聖地霊園の礼拝堂と納骨堂で日本建築学会賞を受賞(1974)し、脂が乗りきっている建築家でもあった。
大学院を卒業するにあたり、健昇は池原から、西武鉄道から依頼された西武球場の設計を手伝わないかと声をかけられる。池原に心酔していた健昇には断れるはずもなく、建築家としても魅力的な大規模建造物の設計というプロジェクトに次々と関わることになる。
池原は長く個人もしくは研究室として設計を請け負っていたが、1988年には池原義郎・建築設計事務所を開設した。健昇は取締役所長に就任し、名実ともに池原の右腕となる。
池原と健昇の幸福な二人三脚の設計ヒストリーにおけるいくつもの代表作は、西武グループの総裁であった堤義明と池原の親しい関係を抜きにしては語れない。パトロンという言葉を超えた、親友に近いともいえるような信頼関係を元に、西武グループから多くの建物の設計を引き受ける。先の西武球場(1979)、西武遊園地(1982)、北九州プリンスホテル(1989)、掬水亭(1990)、広島プリンスホテル(1994)など枚挙にいとまがない。
「厳しい池原先生と、次々と細かい要望を繰り出す義明さんの期待に答えるのは、とても苦しかったけど、とにかく面白かったし勉強になった。最後に『いいもの作ってくれてありがとう』って依頼主である義明さんに言われると、苦労はすべて救わました」
このようにして健昇は、巨大な光を放つ、癖の強い感情的な希代の建築家、池原義郎を30年近く支えることになる。

池原設計事務所での充実
池原事務所は日本全国のバブルの波に乗り、順風満帆で拡大する。健昇は自由奔放にデザインを行う池原を活かすための役割を自ら規定していった。発注の規模やタイミングが読めない西武関連の依頼にだけ依存する訳にいかない以上、定常的に請け負う仕事は主として公共建造物のコンペになる。だがコンペである以上、設計は求められる条件を満たしながら、長い選定プロセスに参加し、勝利しなければならない。デザイン一辺倒では勝つことができず、相手の要望や予算を合理的に処理し折り合いを付けながら、エモーショナルな池原のアイデアやスタイルを実現していく。
「勝率は高かったんです。もちろん池原先生がいてこそなんですが」
健昇は、長いインタビューを通じてこの時だけは少し得意そうな顔をした。
コンペに勝ったら、今度は工期や予算を厳格にコントロールしなければならない。綱渡りのような日々だ。
仕事を受注し、膨大な設計をし、施工の管理をする。それを全部していたのなら、逆に、美味しいところだけ池原に取られている感覚はなかったのか、と少し意地悪な質問をしてみた。
「まったくそんなことはないですね。僕は、池原先生だったらこうするだろう、と考えて提案するわけです。僕は自分のことを一人の建築家だとはずっと思っていなかった。あくまで弟子として池原先生の設計をなぞっていただけだという感覚でした」
そのまま少し時間をおいて、健昇は言葉を続けた。
「僕は小さい頃に父親をなくし、身近に尊敬できる男性はいなかった。池原先生に巡り合い、生きることが建築であるという、生き方そのものを教えてもらったのだと思います」
運命的パートナーとの出会い
陽子は、健昇より八歳年下で青森生まれ。幼い頃から公園など都市の風景が好きだったため、芝浦工大で都市設計を専攻。卒業後、希望していた都市設計事務所に就職する。しかしそこで10年単位でしか仕事が進まない現実を肌で理解した陽子は、改めて建築に進もうと決意し、早稲田大学専門学校(現 早稲田大学芸術学校)の夜間コースに通い始める。
健昇は、そこで講師をしていた。助手として池原のTA(ティーチングアシスタント)を数年務めた後、そのまま池原から設計製図の授業を引き継ぎ(丸投げされ)、設計の傍らで早稲田関連の学校で20年に渡り教鞭をとったのだ。その初期に陽子に出会ったことになる。
「教え子だったんですよ、当時は。今は完全に立場が逆転しましたけど」

当時、早稲田大学が新たに開く所沢キャンパスの設計に没頭していた。時間も予算も制限される中で、教え子たちに頼み込んで、アルバイトとして設計の前調査に動員をかけた際の一人が陽子だった。
健昇は、この時期に前妻を病気で亡くしている。失意のどん底であり意気消沈しつつも、誰よりも深く関わっている所沢キャンパスの膨大な本設計は、どうしても自分が抜ける訳にはいかない。荒んだ一人暮らしをしながら、早朝から深夜まで働き続けた。
当時の健昇はピリピリとした怖い存在で、学生たちから恐れられていたという。名門大学の新キャンパス造成という一大プロジェクトの中核を担う少数精鋭の池原設計事務所は、まさに戦場の前線であり、その現場指揮官だから当然とも言える。
しかし、健昇への陽子の眼差しは少し違っていた。トイレにいってシャツをパンツに入れ忘れる癖、糖分補給のカリントウをボリボリ食べる様子、そのカリントウの袋に片手を突っ込んだまま疲労の余り机で寝入ってしまう姿などを見るうちに、恐れと同時に小さな親しみを感じていくようなる。アルバイトをしていた数か月の間、たまたま帰りの電車の方向が同じだったため、電車の中でポツポツと人生のどん底期ともいえる健昇の話を聞くことになり、距離は次第に縮まった。
こうして二人は付き合い始めた。陽子は卒業後、念願の栗生総合計画事務所(現:北川・上田総合計画)に就職する。種々の巨大プロジェクトが舞い込む中で、陽子も所員として日本各地を飛び回り、一緒に過ごす時間は皆無となったが、逆にその隙間を埋めるように二人は結婚する。しかし、その直後から陽子は京都への長期出張となり、完全にすれ違いの生活になってしまう。
「なんのために結婚したかわからない」
久々に二人で東京で過ごす時間に健昇が小さくつぶやいた言葉に、満身創痍で心が痛んでいる健昇の状況に改めて気づいた陽子は、憧れた末にようやく入ることができた事務所を辞め、同じ職場だったら寂しがらせることもないだろうと池原義郎建築設計事務所に入所する。こうして夫である健昇と上司部下の関係になったのは、バブル真っ盛りの1989年であった。
陽子もそれから10年ほど池原事務所に在籍し、主力の一人として設計を行うことになる。
縮小する事務所から追い立てられるように独立
しかし、池原設計事務所での充実した時間にも終わりが近づいてくる。
バブルが完全にはじけ、世の中が終わりのない長い不況のトンネルの中にあった。不動産開発を積極的に手がけていた西武グループも深い痛手を被り、池原事務所への依頼は途絶えた。健昇は自ら採用した30人ほどの所員を維持することができなくなり、人員削減に踏み込み、陽子も職を失う。もちろん、健昇から特別扱いされることはなかった。
放り出された陽子は自分で事務所を開くことを決め、一級建築士の資格をとり、2002年10月にデザイン・ラボを開いた。名前は、家具などのプロダクト設計も好きな陽子が建築に限らず、広くデザインの仕事をしたいということから名付けた。
一方、所長として人員削減を終えた後、健昇は責任をとって自らも退職する決意を固め、池原に伝えた。池原は黙って辞意を受け入れたという。こうして長い時間を共に過ごした池原の元を離れた健昇は、前年に陽子が設立したデザイン・ラボに合流する。とはいえ、リストラを断行し疲れ切った中ですぐに建築の仕事にとりかかる気にもなれず、ぼんやりとした日々を送ることとなる。

しかし、そこから健昇の人生はさらに大きく動く。きっかけは陽子の父親だ。陽子の実家は青森の曹洞宗の寺院である。そもそも結婚した際、健昇という名が僧侶のような響きを持つことに喜んだ父親は、虎視眈々と跡継ぎにすることを狙っていたのだ。
池原事務所を辞め、無為の時間を過ごしていると聞いた陽子の父は健昇に、僧侶となって仕事を手伝ってもらえないかと懇願した。建築の世界に戻りかねていた健昇は、数週間か長くても一か月程度の研修で僧侶になれるのなら、休養と気分転換も兼ねてそれもいいだろうと願いを聞き入れた。
ところが実際に蓋を開けてみると曹洞宗の修行は二年間かかることが判明する。仏教宗派によって資格取得までの期間は違い、禅宗である曹洞宗はとりわけ長いと知った時には、後の祭りだった。
健昇は、頭を丸め、僧侶養成機関である専門僧堂に通い始めた。50代半ばの身で、筋骨隆々とした20代の兄弟子たちの下っ端として仏事に追われる生活。一日数時間、長い時は10時間以上行う座禅も慣れるまでは苦痛以外の何物でもなかった。
途方もなく長く感じた二年の修行の後、専門僧堂からの免状をもらい健昇は正式に僧侶となる。毎月、東京から青森に通い、木魚を叩き、読経に参加するなど約束通り義父の仏事を手伝い始め、お盆などには青森に常駐することになった。
その矢先の2013年、健昇にガンが発見される。
肝臓ガン、ステージ3。体調不良で受診した埼玉医大で、先行きは長くないという明確な余命宣告を受けた。病院から帰った健昇は、口を開けず、黙々と服や身の回りの品を捨て、身辺整理を始めたという。その様子を陽子は見守ることしかできなかった。抗がん剤による治療を続けるものの、病状は次第に悪化し、肺に水がたまって歩くこともままならなくなってしまう。
陽子は駆け回って情報を集め、様々な治療法や薬、健康法を二人三脚で試した。そして、息を詰めるような数か月がたった頃、奇跡が起きた。突然、腫瘍マーカーの数値が劇的に改善し、完全に正常値に戻ったのだ。教授も「驚くべきことに、もうあなたはガンじゃない」と太鼓判を押してくれた。
その後、2019年に肝臓に再度がんが見つかったが、1㎝程度の小さなものでラジオ波治療で焼ききることができた。その際の血栓などで今でも体調は万全ではなく、体重も10㎏以上落としたものの、なんとか上手に病気と付き合いながら暮らせていると二人は言う。
デザイン・ラボの仕事の変遷
池原事務所のリストラと退所、僧侶修行、病気との闘い。目まぐるしく人生が転換する中、二人の運営するデザイン・ラボも、幾度かの方向修正を余儀なくされる。
時計の針を少し戻そう。
健昇が合流して二人体制になったことで作業スペースが手狭になったため、事務所を近所に構えることにし、二人は1973年に建築された築30年の5階建て250戸の黒須団地の一部屋を購入する。事務所兼住居として全面的なリフォーム、今でいうフルリノベを行った。すると、それを見ていた団地の住民や近所のマンションの人から、同じような改修を行いたいという依頼が次々と舞い込み、二人は期せずして、共同住宅のリフォームの仕事を何件も受けることになる。

しかし、団地リフォームは、食い扶持を稼ぐという意味では喜ばしい話ではあったが、設計者としては非常に難しいものだった。施主はほぼ全員が住みながらのリフォームを希望し、空間を区切りながらの施工になる。時間もかかるし、職人の手配もかなり複雑だ。口コミで依頼は途切れず来るものの、施主側も、設計側もストレスが大きく、その割に一件あたりの金額は小さい。できれば新築をやりたいと夫婦で話し合い、リフォームの仕事を絞り戸建新築に方向転換することにした。
僧侶修行や闘病など私生活が激動だったこともあり、積極的な営業はしなかったが、知り合いの紹介などで戸建新築の設計の仕事はポツポツと舞い込んだ。しばらくの間はその仕事を自分たちのペースでこなすだけで精一杯だった。しかし、そんな中の一つの依頼が、二人の仕事の方向をまた変えることになる。
その依頼は、同じ建築業界にいる先輩の息子から来たものだった。自宅が池原の設計によるものであったが、数十年が過ぎて痛んできた中で息子に代替わりするにあたり、家を壊して新築もしくは大改修を行いたいという話だった。
闘病中ではあったが、師匠である池原が設計した住宅のその後ということもあり、二人は病をおして引き受けることにした。しかし蓋をあけてみると、現在の建物は何度かの増築などを経て、容積率超過の違法建築状態であり、適切な形でのリノベは難しいと判断せざるを得ない状況だった。
話し合いを続ける中で、希望を可能な限り満たし、長期での資産価値を高めるために新築に建て替える、という大方針をようやく施主に受け入れてもらうことができた。健昇は、体調に気を使いつつも丸一年かけて実施設計に邁進した。工務店の見積を三社からとり、予算をオーバーする部分は施主の希望をギリギリまで叶えながら要件を削り、ようやくあと一回の打ち合わせで本契約という段階までこぎつける。
しかし、その最後の打合せで、施主は
「よく考えましたが、値段も高いし、面積も狭くなる。やはり新築はやめておきます。大手のリフォーム会社に頼むことにしました」
と二人に告げた。隠れて別の話を進めていたのだ。精魂尽くした設計は水泡に帰した。いま振り返って、二人はこの「事件」は本当に大きかったという。
「こういう仕事はもうまっぴらだと思いました。思えば、池原先生もやりたくないものからは徹底的に逃げ回っていました。どうしても仕方ないときは弟子にやらせて。まあ僕には弟子はいませんから、ただただ好きなものをやろうと思ったんです」
こうして、クライアントの要望を叶えるリフォームや新築ではなく、自分たちがこれはと思う割安な物件を購入し、自分たちのやりたいようにリノベーションし、自分たちが売りたいという価格で売る、いわゆる不動産の買取再販を始めることになる。
買取再販を行うと決めた理由
一般的な買取再販は、とにかく安い物件を仕入れて、壁紙などで最低限の化粧をし、割安に販売する。しかし、デザイン・ラボは全く違う。二人は「自分たちが住んでもいい」と思う空間を創ることを絶対的な基準としている。そして、その「自分たち」とは一流の建築家であり、エリアの不動産情報に精通し、リフォームの経験も豊かな二人組なのだ。
「割安だが魅力あるマンションを買って、自分たちの気に入る空間を創り、その実物を見て納得して買ってもらうというのが、誰にもストレスがかからず、自分たちらしいのではないかと思ったんです」

ただし、現実的な問題が二つあった。一つは資金である。健昇の闘病の中で二人にはほとんど収入がなかった。生活費は蓄えなどでギリギリまかなっていたが、到底、マンションを買う原資はない。銀行が貸してくれるとも思えない。この問題は、結果的に高齢の健昇の母を拝み倒して資金を借りることで解決した。もし彼女のサポートがなかったら無理だったと二人は言う。
もう一つは、法律の問題である。不動産を頻繁に個人が売ったり買ったりすることは、宅地建物取引業法にて明確に禁じられている。買取再販を継続的に行うためには、業として、宅建免許が必要になるのだ。この問題は、健昇が猛勉強し宅建免許を取得するという正攻法で乗り切った。と、一文で書くと簡単そうに見えるが、年に一度しか開催されない宅建免許は、毎年合格率15%前後の難関資格だ。とてつもない知性とバイタリティーである。
もともと建築や不動産が大好きで、誰よりも専門家である二人にとって、物件を探す、リノベの設計と施工管理は、もちろん一般人と感覚は違う。経験も自信もあったが、実際に最初の物件が売れた時には本当に安心したという。
「最初は設計料の感覚で、1000万の物件だったら10%のせて1100万円程度の値段を付けていました。でも商工会議所に相談したら、売買はリスクもあるし、そんな値付けをしていたら、一つ失敗したら潰れてしまいますよとアドバイスを受けたんです」
と陽子は笑う。二件目からは、利幅も少し多めに乗せることとしたが、それでも売れた。今では、ほぼ目論見通りの安定感が出てきたが、何より、日々のストレスがなくなり、原点である空間設計を行う純粋な喜びを感じながら仕事をすることができるようになっている。
デザイン・ラボの家を買う人
それでは、どんな人が二人の物件を買っているのか。
池袋駅から特急で30分かかる入間は、付加価値の高い不動産の取引が活発な街ではない。南口には地元百貨店やシネコンなど商業施設が栄える一方、北口は出るとすぐにマンションや団地など築数十年の集合住宅が並ぶ。入間市駅の一日の乗降人数も1995年の3.6万人をピークに30年に渡ってなだらかに下がっている(2007だけは大型施設がオープンしたため例外)。

住みやすい街なのは間違いない一方で、率直に言えば個性の薄いベッドタウンである。芸術や創造といった文脈とはやや縁遠い。そのような地域で、二人の物件は、こだわりの空間を実現しているがゆえに、面積単価などのわかりやすい指標でみると周辺相場よりも少し割高に見える。どうやって買い手を見つけているのか。
「R不動産あってこそなんです」
嬉しい言葉だ。二人が力を入れリノベしたマンションの購入者は、一件を除いては全部、R不動産を介した買い手だという。しかもその全員が元々入間市に住んでいない、都心からの移住者だ。
どういうことか。不動産を探すとき、エリアや最寄り駅から探す人が多数派だ。しかし空間の魅力から探す人も確実に存在する。建築への感性を持つ人は、エリアに縛られず、自分のテイストにあった空間を持つ物件を探し、雑誌を見るかのようにR不動産のサイトを回遊してくれている。
例えば、二人は最近、73.71㎡の広さで駅徒歩5分の築35年を経たマンションを2,750万円で販売していた。築年数と面積と比して2,750万円という金額は入間市の物件としては少し割高だ。しかし逆に、この物件を東京23区内で購入しようと思ったら到底この金額では無理だ。

二人の空間に惚れ込み、リモートワークができたり電車で30分強の通勤時間を苦にしない人ならば、「まさにこれだ」と思う人がいてもおかしくない。そういう人こそが二人の顧客になりうるのだ。
「元からこの辺りの住民の方だと誰も買わないかもしれません」
実際、当初、地元の不動産屋にいったときには、売れないから値段を下げろと一蹴されたという。
実際の購入者はどんな人なのか
たまたま現在の事務所とギャラリーが入っている建物の6Fの、デザイン・ラボがリノベ再販した物件をR不動産経由で購入した岡村さんに話を聞くことができた。

岡村さんは、R不動産で実際に契約したことこそなかったが、サイトは以前から時々眺めていたという。コロナになり、在宅では今の住居が手狭になってきたと感じていたときに、R不動産のこの物件が気になって初めて連絡をとった。元々は駒込在住で、入間とは縁は全くなかった。職業はIT系の営業職で、仕事先は横浜である。入間市駅から直通電車が出ている(西武池袋線〜副都心線〜東横線)ことは大きな魅力だった。
「まったく土地勘もなく、プチ移住くらいの感覚」
仕事先が都心ということもあり、買い物なども特に不便がなく、むしろ、自宅作業の日に都心とは違う空気感の中でゆっくり仕事できるのも魅力だという。アウトドア好きの岡村さんが物件を気に入ったポイントは、窓の外の山が見える景色と、家のデザイン、そして価格。この広さと環境に対しての価格は、都心では到底実現困難だ。それまで住んでいた駒込も、賃貸だったら何とか住めても、買うのは難しいと感じていた。そう考えたときに全部がしっくりはまった。

「いろいろ探していて出会ったというよりも、定期的にR不動産を見ていて『びびっ』ときた感じ」
もちろん、他の選択肢も検討はした。いくらくらい出せばもう少し都心に近づけるのか、入間で同じような価格帯だと他にどんな物件があるのかなど。でも結局は直感で決めたという。
実際に住んでみて、立地も環境もとても気に入っている。家の中で特に気に入っているのは、床材。他の物件見てもあまりない床材で、キッチンのラワンの感じもいい。造作棚、キッチンのタイルもお気に入り。
エントランスを出るときに事務所にいる奥様(陽子)と目があうと、笑顔で手を振ってくれたりする。密にコミュニケーションをとるわけではないが、そばにいる感じ。ギャラリーでも、二週間に一度ぐらい展示が変わり、作品のクオリティも高い。ギャラリーを営む方としても、すごくセンスがいいなと感じている。
夫妻を介して申し込んだインタビューとはいえ、べた褒めなのである。

やりたいことは、まだまだある
河野夫妻に、今後どのようにリノベ再販事業を広げていきたいのか聞いてみた。
「今は青梅、入間を中心にやっていますが、いずれもっと都心で勝負したい。それに、マンションだけでなくて、最終的にはやはり戸建てをやりたいんです。上の階段に登っていきたい」
事業欲旺盛な健昇である。陽子が後を引き取る。
「それから、もっと質の良いものも追及したい。本当の建築家の仕事の水準から見ると、今創っているものにはまだ不満がある。コストも膨らむが、もっとずっと良いものを創れるし、私たちが作るものには、絶対に住みたい人がいるはず。良い空間を理解できる人をR不動産が連れてきてくれる」
R不動産への賛辞はありがたく受け取りつつ、絶対に顧客がいるはずだという自信がどこから来るのか聞いてみた。健昇が答える。
「本来、日本人は感性豊かなのです。それなのに四季を楽しめない貧相な建築の住宅ばかり。自然と一体になった、良いものを見せれば、その中で暮らしたいという人は絶対にでてくる」
設計欲と事業欲はどちらが強いのか。
「再販を始めて、いろいろな人たちに出会うことができたし、僕たちもささやかに暮らしていくことができる。次第に大き目の物件にも挑戦できたりもする。だから事業の喜びは間違いなく感じています」
健昇が言葉を選びながら続けた。
「でもね、施主さんなり買い手さんなりの『いいもの作ってくれてありがとう』という言葉を聞いた時の高揚感は何にも代えられない。最高の喜びです。その意味で、設計欲の方は絶対に譲れないですね。設計はやっぱり面白いですよ」
そして、不動産再販は常に「街」に対する問題意識を持ち続けている陽子にとっての解決策でもある。採算度外視のアートギャラリーを設けているのも、陽子が建築士会の入間代表を務めるのも、「入間市の文化遺産をいかす会」など様々な地域活動で汗を流すのも同じ理由である。
「良いものを創ることで入間に若い感性の人を連れてきている自負はあります。少しづつでも、入間が文化を持つ街になっていって欲しいし、私はここで私の領域である空間文化を豊かにしていきたい」
街を活性化させたいという思いを力強く語った後、陽子は最後に、茶目っ気と使命感にあふれたコメントを発した。
「都市空間を学んだ私にとって、例えば入間市駅の改札を出ると、すぐに公衆トイレがあって、あろうことかトイレの入り口が駅を向いていることはあり得ません。街に入るといきなりトイレの中をみせられるのです。これではダメです」

ささやかな革命と街の進化
さて、ここからは僕たちの、ある意味で手前勝手な解釈である。
一言で言うなら、河野夫妻こそ、生粋の建築家であるのと同時に、好奇心にあふれ、人生を楽しむ事業家であると感じた。
入間という必ずしも建築家として魅力的とは言えないマーケットで、力技とも言える二人の創作のパワーで不動産のリノベ再販という事業を成立させている。二人がやっていることをある角度から切り取れば、建築家にとってのまさに新しい形での職能モデルだと言える。二人のような仕事をしたいと心から感じる建築家は多いだろう。
しかし、二人は自らを大きく見せるような手段を取らず、キャリアを通じていわゆる営業活動のようなこともほとんどしていない。かといって、野望や次の挑戦を聞くと堰を切ったように溢れ出る。失礼ながら、健昇さんは古希を超えた年齢だが、自ら図面を引き、現場で施行の監督を行いながら、高い理想も熱く語るのである。
その根底に流れる自信や動機の源泉を聞くと、自分たちのスキルや経験という以上に、日本人の美意識と、自分たちを育ててくれた師匠、ひいては建築という学問領域への深い信頼であるように感じた。だからこそ二人は静かで強い。

河野夫妻のような方が日本の津々浦々で、設計者の感性が練り込まれた物件を続々と産み出し提案する。そして、その空間、環境、スタイルなどに共感した人が地域の枠を超えて移り住み、好奇心を満たし、望んでいた住空間や生活を手に入れる。そういった世界を実現することが、R不動産という我々のサービスのミッションであると思う。
リノベ再販は、難しいバランスの上にたつモデルだ。マーケティングのバランス感覚を持たない建築家にとっては非常に危険とも言える。元の物件を高く買ってしまったら、リノベの方向や質感を間違えたら、値付けを失敗したら、集客ができなかったら、というトラップがいくつもある。誰もに安易におすすめはできない。しかし、それでも、僕たちはそんな世界を夢見てしまう。
楽々とその難しい世界を実現している二人を見て、健昇さんの建築家としての本質的な強さと、陽子さんのマーケター(建築家でもあるが)の強さが融合して、類まれなる最強ユニットになっていると感じた。そしてその前提なのか、結果なのか、二人はとても仲がいい。
建築家をあえて大別すると、人間を優しく包む空間を創ることを重視するタイプと、ジャーナリスティックで斬新な建築を志向するタイプに分かれると思う。健昇さんの師匠、池原義郎は、前者と言えるであろう。その薫陶を誰よりも近い場所で浴び続けた健昇さんが、人々の生活と街を、建築の力で優しく変えるような今の場所にたどり着いたのは必然とも思える。
二人は、つまらない建物ばかりが増え、豊かな空間が減っている日本の状況を少しづつ変える、ささやかな革命家のようだ。小さな石を置き続け、その積み上げがじわりじわりと街に何かを産み、継承され、何かが変わっていく。僕らは、このようなささやかな革命家を支える存在でありたい、と改めて感じた。

語り手:河野健昇さん・河野陽子さん
デザイン・ラボ 一級建築士事務所:https://d-lab-arch.com/
取材・構成:渡辺 雅之 / 写真:阿部 健二郎
-
 Vol.007安藤さんと大蔵の地語り手:安藤勝信さんあとから来るもののために100年後に思いを馳せる。安藤さんと大蔵の地の物語
Vol.007安藤さんと大蔵の地語り手:安藤勝信さんあとから来るもののために100年後に思いを馳せる。安藤さんと大蔵の地の物語 -
 Vol.006杉田さんと「アカバネの森」語り手:杉田由樹さんクリエイティブなオーナーたちが生み出す、他にない物件。杉田さんと「アカバネの森」の物語
Vol.006杉田さんと「アカバネの森」語り手:杉田由樹さんクリエイティブなオーナーたちが生み出す、他にない物件。杉田さんと「アカバネの森」の物語 -
 Vol.005小谷さんと小上がりのある書店「葉々社」語り手:小谷輝之さん思いが込められた物件が、魅力的な借り手を引き寄せる。小谷さんと梅屋敷「葉々社」の物語
Vol.005小谷さんと小上がりのある書店「葉々社」語り手:小谷輝之さん思いが込められた物件が、魅力的な借り手を引き寄せる。小谷さんと梅屋敷「葉々社」の物語 -
 Vol.004中屋さんと「わたしの熱海の家」語り手:中屋香織さん移住は理想の暮らしを手に入れる手段。熱海で自分らしい暮らしを手に入れた中屋さんの物語
Vol.004中屋さんと「わたしの熱海の家」語り手:中屋香織さん移住は理想の暮らしを手に入れる手段。熱海で自分らしい暮らしを手に入れた中屋さんの物語 -
 Vol.003街のささやかな革命家語り手:河野健昇さん・河野陽子さん豊かな空間で街を変えていく。郊外でリノベ再販事業を手掛ける建築家夫妻の物語
Vol.003街のささやかな革命家語り手:河野健昇さん・河野陽子さん豊かな空間で街を変えていく。郊外でリノベ再販事業を手掛ける建築家夫妻の物語 -
 Vol.002麻生要一郎さんと「カスティロ」語り手:麻生要一郎さん新・雑居世界のはじまり。麻生要一郎さんとマンション「カスティロ」の物語
Vol.002麻生要一郎さんと「カスティロ」語り手:麻生要一郎さん新・雑居世界のはじまり。麻生要一郎さんとマンション「カスティロ」の物語 -
 Vol.001江頭さんと「DOTEMA」語り手:江頭豊さん物件と人の物語を綴るコラム第1回。東京・池ノ上に佇む複合スペース「DOTEMA」の物語
Vol.001江頭さんと「DOTEMA」語り手:江頭豊さん物件と人の物語を綴るコラム第1回。東京・池ノ上に佇む複合スペース「DOTEMA」の物語


















![[団地を楽しむ教科書] 暮らしと。](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/rincglobal/common/thmb_kurashito_book.png)