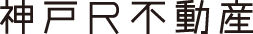第19話 東武ビルディングは何処へ向かうのか(其の二)
浅草は今日も沢山の人だかり。スカイツリーもいよいよ500mを超えて予定では竣工を1年後に控える様になった。観光客はスカイツリーを見上げて色めき立つが地元ではそろそろ普段の景色に同化し始めている気配も感じられる。新しいものに対しては比較的寛容で状況の取り込みも早い独特の気風ゆえだろう。前回は東武ビルディングのワンフロアーに台東区特有の「モノ創り」の文脈でショップ・ギャラリーを集積させ観光客・地元民にも台東区の魅力を駅上の百貨店で一堂に感じて貰い購買に繋げるプラン(というか、妄想)のお話をした。今回はそもそも宿泊客を駅上に取り込んでしまおうと云うお話です。

東武線ガード下より東武ビルディング北側を見上げる。
例えば外国人観光客が東京に来た場合、旅行のスタイルにも寄りますが旅慣れた旅行者は比較的日本の古い要素が残っている浅草界隈に日本独特のスタイルを求めて宿を取るケースが多い様子です。界隈にドミトリー(いわゆる相部屋式)などのホステル(簡易宿泊所)形式の宿泊施設が独自に発展を遂げている理由も理解が出来ます。独自の進化を遂げる「秋葉原」、古き良き「谷根千界隈」、そして地下鉄銀座線を使えば「浅草~渋谷」まで一本と、沿線には最新の人気のエリアが広がります。浅草は旅のスタイルも宿のスタイルも其々自由に選べる「日本旅行」の起点としてツーリストに人気の場所で在ることがお解り頂けるでしょうか。

階段にて500m以上駆け上がるの図。
更に旅行者を受け入れる地元にも特徴があります。浅草寺を中心に同心円状に商業エリアが広がり、初めて浅草に降り立った旅行者にも街の理解が早い。古くから栄えた分お店同士業種の棲み分けも進んでおり、横の繋がりも比較的密接なので「~が欲しい!」と言えば「それならあっちだよ」と気軽に教えてくれる気風もある。参道沿いの土産物屋さんに始まり、昼間から一杯飲める半屋台的な店が軒を連ねる通称「ホッピー通り」。更には「観音裏」に拡がる、一見では非常に入りづらい名(迷)店の数々は浅草の懐の深さを垣間見ることが出来る。レベルと感性に応じて選択肢の幅が広いのが浅草界隈の魅力である。

この奥、本堂大営繕もめでたく完成しました。

こんな昭和な楽しみ方もありありな浅草。
いっその事、旅の起点である東武ビルディングの最上階7階に宿泊施設を創ってしまっては如何だろうか。旅のレベルに応じて快適に過ごせる豪華な個室から相部屋で一泊まで、様々なニーズに対応出来る空間。敢えて様々なタイプの旅行者が泊まる事で情報の交流が活発になる様な仕組み。勿論主眼に置くのは東武ビルディングが本来持つデザイン性の高さ。日本の極め細やかなおもてなしの心に決して華美ではない機能重視のファシリティーの数々。
駅上の百貨店の上階に宿泊施設が在るという意外性と安心感等々。

中谷ノボル( Arts & Crafts)さんが手がけた HOSTEL 64 Osakaがお手本になる。
クリアーしなければならない基準はままあれど世界一高い自立式電波塔を立ててしまう技術力・調整力をもって掛かれば不可能では無い筈。スカイツリーの対極に昭和の古き良き遺産を最大限に活用し未来に繋げる構想であれば東京の玄関口として東武ビルディングが世界に誇れるターミナル・デパート・ホテルになる筈です。
余談ですが松屋浅草店屋上にあった日本最古の屋上遊園地である「プレイランド」には当時隅田川を越えて屋上と対岸を結ぶゴンドラが計画されていた様で当時の飛び抜けた熱気や発想力が伝わる事例として引き合いに出したい。浅草・東武ビルディングの、2010年5月31日に閉鎖された4階から7階、そして屋上に、再び活気が戻る為には溢れんばかりのおおらかさと周到なマーケティングが必要になる事でしょう。東武ビルディングの活用プラン(妄想)はまだまだ続く。

(写真出典:社史編集委員会編『松屋百年史』株式会社松屋・発行 1969年)
 このブログについて
このブログについて浅草エリアの時代がやってくるのではないか?!それが私たちの仮説です。日本橋エリアを見つけた時の感覚と同じものを、東京のさらに東側の浅草エリアに感じました。昭和の懐かしさと近未来が混在したシュールな風景がおもしろいこの街で、物件を探し始めます。
浅草を探索する理由とは?
馬場正尊による関連コラム
「気になっている浅草エリアを、自転車ツアーで探索してみる。」
 著者紹介
著者紹介三箇山、松尾、伊藤、黒田(山形R 不動産リミテッド)
東京R 不動産の東チームとして日本橋エリアの物件を開拓するメンバーと、1 ヵ月の限定の特別参加の山形R 不動産リミテッドからの学生インターン。


















![[団地を楽しむ教科書] 暮らしと。](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/rincglobal/common/thmb_kurashito_book.png)