
みんデベを監修・サポートするArea development lab.のディレクターへのインタビュー。第2弾として大月敏雄さんにお話を聞きました。
東京大学大学院工学系研究科の教授である大月さんは、建築から都市まで、デザインから福祉まで、軽やかに横断しながら、深い洞察と温かい語り口で、僕らを知の世界に導いてくれる人。そんな大月さんに、都市や建築の文脈の中でみんデベに期待されるものとは何か、聞いてみました。
――大月さんは、みんデベという動きや、ここで生み出される手法などに、どんな意味があると考えていますか?
大月敏雄(以下、大月)
都市の整備や使い方、まちづくりの手法・手段というのは、いろいろと考えられるはずなのに、我々はまだほんのわずかしかそれを持っていないですよね。みんなで実際にやりながら、そういう手法論みたいなものを整理していけると面白いと思っているし、それはArea development lab.の活動の動機でもあります。
――例えばどんなことが期待できそうですか?
大月
例えば都市計画法でいうと、都市計画のなかで整備・開発・保全の方針を明記するようになっているんです。そのなかでも僕は「整備」というものに可能性を感じています。そのエリアが備えるべき条件を整えるという意味ですが、すでに開発され、住まわれているエリアを、もう一度検討して、その時点において必要な備えを整えることだと、僕は解釈しています。これに対して、都市をゼロベースでつくるのが「開発」だとすると、「整備」では「開発」とは異なる手法や収益構造のあり方が考えられるべきでしょう。まちづくりのようなボトムアップの動きでも、ファイナンスの課題をどう解くか、マネジメントの技をどう伝えていくかというようなところも課題になってくると思います。「整備」の例でいえば、学園町(東京都東久留米市)で住宅街の環境を乱開発から守る取り組みを、R不動産も一緒にやっていると聞いたけど、そういう具体的なフィールドでの動きに期待しますね。
林 厚見(以下、林)
学園町は100年ほど前に自由学園が開発したまちで、1区画が500㎡以上ある緑豊かな環境が魅力だったのですが、相続などでどんどん細分化されて、残念なまち並みになっていってる……。僕らは「HITOTOWA」と協働して、コーポラティブの手法を使うことで、環境を守りながら引き継いでいく取り組みをしています。
大月
2022年に騒がれた生産緑地解除の問題も同じだけれど、農地があって、その環境の魅力を前提に周辺も含めたまちが形成されているのに、それを無視して開発の論理が持ち込まれ、1haの開発と同じことを500㎡でやってしまう……。そういう乱暴なやり方に、一石を投じるような対案をみんデベが提示することに期待しますね。

林
まちづくりの機運はいろいろな地域で常にあるんだけど、大資本がガサっとやる動きに負けてしまう。それに対して、これまで僕らは大資本の手が届かない“隙間”を狙う動きをしてきたんですが、みんデベの手法を市民が手に入れることで、これまでのデベロップメントを置き換えるようなやり方ができる。そういう時代になってきた、というのが僕らの実感です。
大月
デベロッパーの場合には、儲かるかどうかで判断するし、利益を確保するためにこういうやり方をしなければいけない、という論理になるじゃないですか。再開発事業は、こうすれば補助金が何億円もらえるという図式が決まっているから、全国どこの駅前も同じ風景になるし、それ以外のことにはチャレンジしない。一方で、まちづくりの場合は、時間がかかってもいい、利益が少しでもいいから、まちを良くしたいというつくり方だけれど、限界がある。それを乗り超えるやり方として、みんデベがあるということですよね。
林
パブリックマインドを持った企業とか、力を持っているけど地元のためには利益最優先ではないスタンスを持っている、みたいな面白い人たちがそこら中に出てきている。彼らはまちに対してちょっと面白い発想を持って、ファイナンスのリテラシーも高い。そんな人たちがチームを組んで、コーポラティブの手法を使って事業を組み立てると、無駄なコストなく、それぞれのニーズに合ったものをつくり、価値を上げることが成立してきます。それはリスクヘッジのために同じものを金太郎あめ的につくるやり方とは対極にある世界ですね。

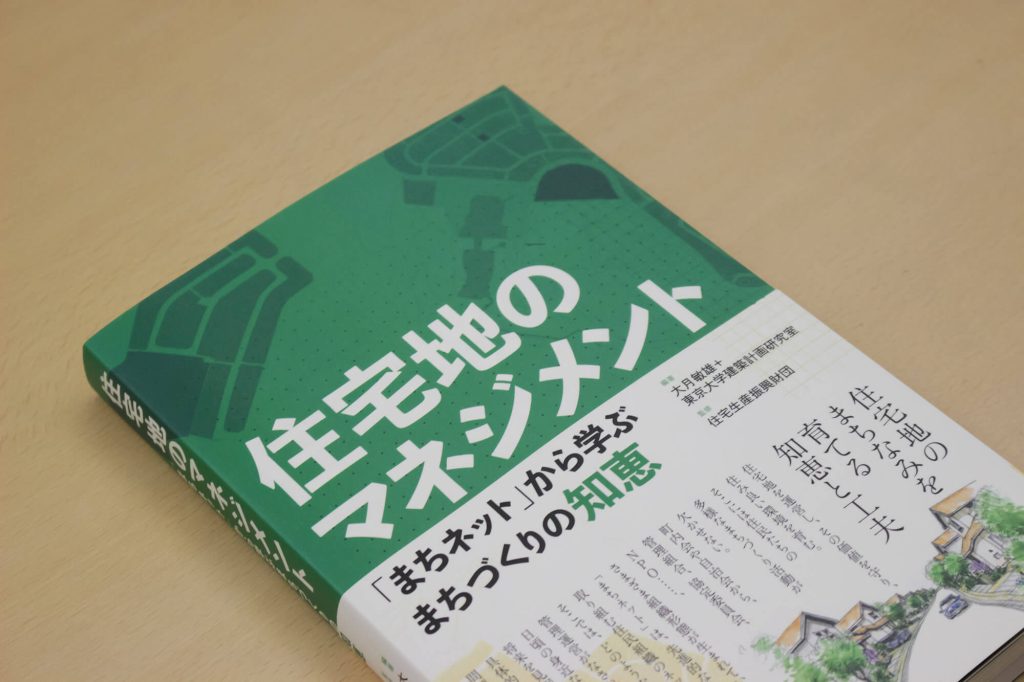
大月
都市がつくられるときに、誰がつくるかということと同時に、どんなスケールでまちを見るのか、という点があると思います。都市計画の人たちは、1/1,000や1/10,000の縮尺で都市を見ている。細かく計画する場合でも、1/500まででしょう。一方で建築の人たちは大きくても1/200までの縮尺で空間を考える。模型を作るときも、1/200より小さいと人間の身体感覚が分からないからだと思います。つまり1/200から1/500の間は、誰も見ていない場合が多い。それを実感したのが、阪神淡路大震災でした。当時、僕は博士課程にいて応援で現地に入ったんだけど、都市計画の人たちは「都市の軸が……」とか「市街地再開発事業で駅前を……」っていう話をしている。片や建築の人はかっこいい集合住宅ができた、という話になっている。その間のスケールで考える人がいないことに気付かされたんです。
――大手デベロッパーと、まちづくり活動と、同じような構図ですね。
大月
さらに阪神淡路大震災で印象的だったのは、ベトナム人のコミュニティ。彼らは公的な支援を受けずに外国からお金を集めたりNGOから物資をもらったり、あらゆる手段を使って自分たちで環境をつくっているんですよ。僕はスラムの研究をしていたからフィリピンとかタイ、インドとかのスラムを回って、すごくいい感じの広場とか路地、良さげな喫茶店なんかができて、夜は夜で楽しい場所になっているのを見てきていた。もちろんヘベレケのおっちゃんとかがいるんだけどね。それと同じような、面白くていい環境を被災地のベトナムの人たちがつくっているのに対して、日本人はブロイラー小屋みたいなところにおとなしく住まわされている……。
――自分たちでまちや環境をつくる姿勢と、供給を待つだけの消費者的な態度。ギャップが鮮明だったんですね。
大月
これは日本の都市計画の問題でもあって、戦後の復興計画をやった石川栄耀っていう都市計画の大家は、飲み屋があるような夜のまちが大事だっていってるんですよ。そんなセンスが、現代的な都市計画になる過程で“漂白”されてしまった。つまり、1/200から1/500あたりのスケールが、夜の盛り場なんかを漂白する舞台になって、そこが消えてしまった。同時に、この縮尺の差を飛び越える想像力をもった人がいない都市計画や建築の課題に行きつくんです。
林
建築や都市計画の場合、戦後の都市化や住宅不足の中で、数の供給をどうさばくか、という時代があった。そこは頑張ったけど、数が足りたときに、質への転換という機運をつくっていくことができなかったですよね……。今は機運という意味では、みんデベに向かう機運の入り口になるようなものがいろいろなところにあると思います。例えば、60代のおじさんたちだって将来の孤独みたいな課題があるはずで、それは福祉とかコミュニティにつながるし、都市計画とか、まちづくり、あるいは不動産の開発・整備で、新しい機運の入り口になるかもしれないし、政治的なパワーになり得る。
大月
生産緑地が解除されて乱開発されてしまう問題だって、そういう福祉を絡めてもっと違うやり方も考えられるし、R不動産が提案しているような、生産緑地を真ん中に残して住居と共生させて地域価値を高めるようなモデルもありだなと思う。2000年以降、そういう知恵は蓄積している印象を持っているけれど、認識や広がりが不十分。だから「あの地域にはあの人がいて、頑張ってる」っていう人に紐づいた情報にしかなっていないですよね。これから、人に紐づいた手法を、みんなの手法として整理していくことの意味は大きいと思ってます。

東京大学大学院工学系研究科/建築学専攻 教授/復興デザイン研究体 特任教授/高齢社会総合研究機構 副機構長
1967年福岡県生まれ。横浜国立大学工学部建設学科助手、東京理科大学工学部建築学科准教授を経て現職。専門は建築計画、建築設計(一級建築士)、住宅地計画、まちづくり、住宅政策。著書に『近居ー少子高齢化の住まい・地域再生にどう活かすか』(編著、学芸出版社、2014)、『住まいと町とコミュニティ』(王国社、2017)、『町を住みこなす』(岩波書店、2017)、『市民がまちを育む-現場に学ぶ住まいまちづくり』(編著、建築資料研究社、2022)など。
